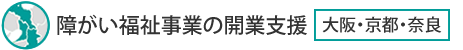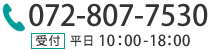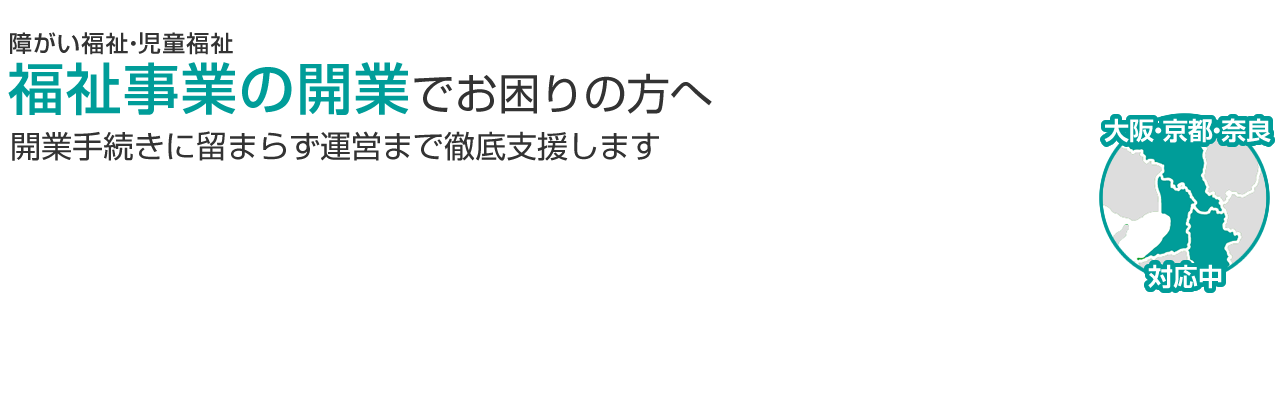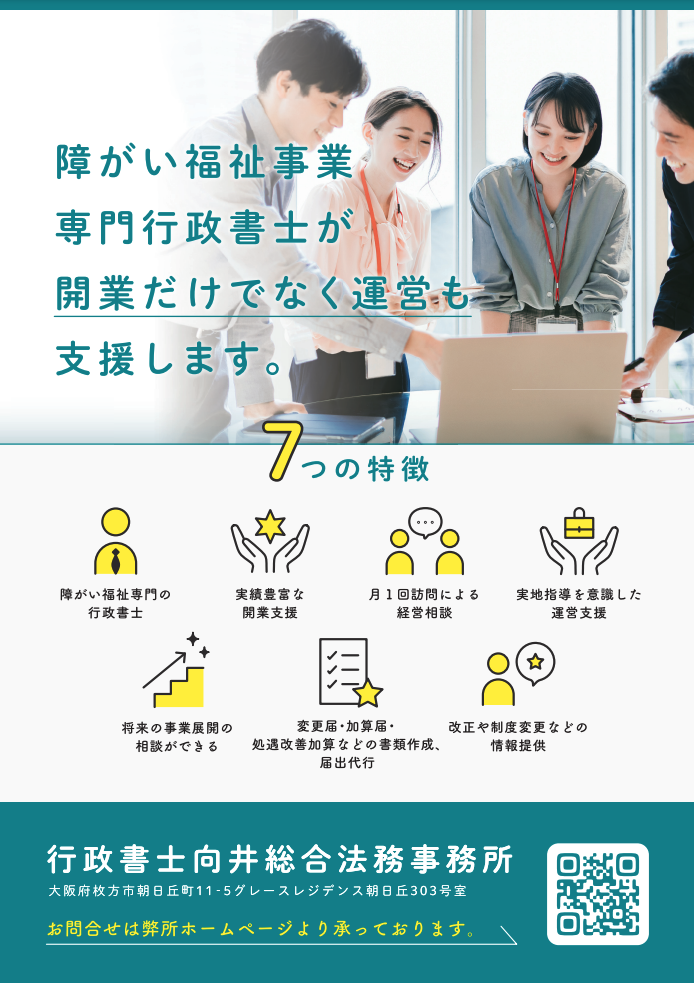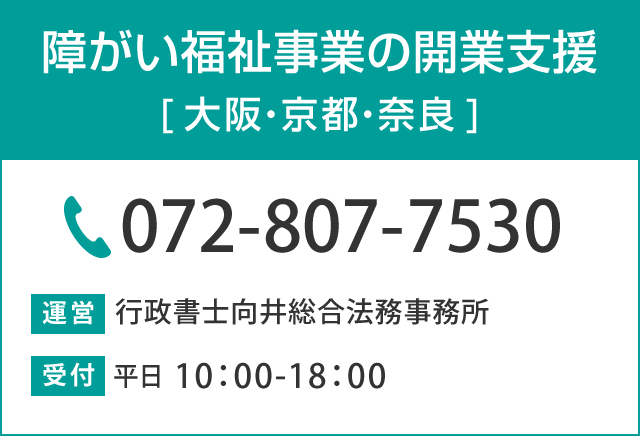【相談事例】就労継続支援B型の事業所で目標工賃達成指導員配置加算を算定しているが、施設外就労の人員配置は「5:1」になるのか?「6:1」でいいのか?
![]()
相談者:就労継続支援B型の経営者
就労継続支援B型を経営しています。報酬算定上の必要な職員配置は「6:1」で算定しています。ただ、目標工賃達成指導員配置加算を算定しているので、施設外就労の人員配置を考える際にも目標工賃達成指導員配置加算を算定する際の要件である「5:1」の人員配置が必要になるのでしょうか?
![]() 回答:障がい福祉専門の行政書士
回答:障がい福祉専門の行政書士
結論から申し上げますと、目標工賃達成指導員配置加算を算定している場合であっても、報酬算定上の必要な職員配置を「6:1」で算定しているのであれば、施設外就労の人員配置も「6:1」の配置でかまいません。
目標工賃達成指導員配置加算を算定する場合、目標工賃達成指導員は本体施設に配置する必要があり、その本体施設では職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員を含めた人員配置は5:1である必要があります。
ただ、目標工賃達成指導員の業務内容は、利用者の工賃向上への取組みにありますが、その業務は本体施設の利用者に対しても施設外就労の利用者に対しても提供可能な業務内容です。
そのため、本体施設に配置された目標工賃達成指導員であっても施設外就労の利用者に対して工賃向上の支援を提供することは可能ですので、施設外就労の利用者に対して目標工賃達成指導員配置加算を算定することは可能ということになります。つまり、施設外就労の人員配置は、「5:1」ではなく「6:1」の配置でOKということです。
施設外就労先では、人員配置基準に応じて、報酬算定上必要とされる人数の職員を配置する必要がありますが、ここには賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は含まれません。基本報酬を算定するうえでの人員配置に賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は含まれないからです。
目標工賃達成指導員配置加算の算定要件
目標工賃達成指導員配置加算を算定するには、以下の算定要件を満たしている必要があります。
①目標工賃達成指導員を常勤加算方法で1人以上配置すること(目標工賃達成指導員に資格要件はありませんが、職業指導員や生活支援との同時併行的な兼務はできません)。
②職業指導員及び生活支援員の総数が常勤加算方法で6:1以上であること(就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)or 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定していること)。
③目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上であること。
④工賃向上計画を作成していること。
上記の算定要件③で、目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員の総数が常勤加算方法で「5:1」以上であること・・・とありますので、目標工賃達成指導員配置加算を算定している場合には、本体施設の人員配置のみならず施設外就労の人員配置を考える際にも「5:1」以上の人員配置が必要になるのではないか?という疑問が出てくるのです。今回の相談事例もこのような疑問から当事務所の顧問先様から寄せられた相談内容となります。
また、目標工賃達成指導員配置加算を算定している場合ですので、職業指導員+生活支援員の人員配置は「6:1」以上であることが前提となります(算定要件②)。
施設外就労の人員配置
施設外就労の人員配置を考える際には、「本体施設」と「施設外就労」の人員配置を別々に考える必要があります。
本体施設
「前年度の平均利用者数」に対して、報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)の職員を配置します。
報酬算定上必要とされる人数というのは、報酬を算定する際に必要となる人員配置(10:1 or 7.5:1 or 6:1)で計算された人数です。
例えば、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定するには、人員配置を6:1で配置する必要があります。前年度の平均利用者数が15人の場合は、15人÷6.0=2.5人分(常勤換算方法による)の人員配置が必要ということになります。
本体施設は「1週間」の所定労働時間を基準に考えますので、1週間の所定労働時間が40時間である場合には、40時間×2.5人分=100時間/週の人員配置が必要になります。
※職業指導員か生活支援員のどちらか1人は常勤である必要があります。
施設外就労先
施設外就労を行う「日」の利用者数に対して、報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による)の職員を配置します。
報酬算定上必要とされる人数というのは、報酬を算定する際に必要となる人員配置(10:1 or 7.5:1 or 6:1)で計算された人数です。
例えば、就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定するには、人員配置を6:1で配置する必要があります。ある日の施設外就労の利用者が15人の場合は、15人÷6.0=2.5人分(常勤換算方法による)の人員配置が必要ということになります。
施設外就労は「1日」の所定労働時間を基準に考えますので、1日の所定労働時間が8時間である場合には、8時間×2.5人分=20時間/日の人員配置が必要になります。
- 報酬算定上の必要とされる人員配置は6:1。
- 目標工賃達成指導員配置加算を算定。
- 前年度の平均利用者数は18人。
- 1週間の所定労働時間40時間
- 施設外就労を行う「日」の利用者数は10人。
- 1日の所定労働時間8時間
本体施設では、
- 18人÷6.0=「3.0」の職員(職業指導員、生活支援員)の配置が必要(算定要件②)
- さらに、目標工賃達成指導員配置加算を算定しているので、18人÷5=「3.6人」の職員(目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員)の配置が必要(算定要件③)。目標工賃達成指導員を含めた職員の配置が3.6以上必要ということです。
- ただ、目標工賃達成指導員配置加算の算定要件として、「目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1以上配置すること」(算定要件①)とあるので、3.0+1.0=「4.0」の職員(目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員)の配置が必要。結局、上記のモデルケースでは目標工賃達成指導員を含めた配置は「3.6」では足りず「4.0」の配置が必要ということです。
- 週の労働時間で考えると、目標工賃達成指導員と職業指導員と生活支援員の合計で4.0×40時間(1週間の所定労働時間)=160時間(常勤加算方法による)の労働時間が必要ということになります。
施設外就労先では、
- 10人÷6=「1.7」(小数点第2位切上げ)の職員の配置が必要になります。
- 1日の労働時間で考えると、1.7×8時間(1日の所定労働時間)=13.6時間(常勤換算方法による)の支援員の労働時間が必要ということになります。
本体施設で目標工賃達成指導員を配置し目標工賃達成指導員配置加算の算定要件を満たしているのであれば、上記の施設外就労の人員配置基準をクリアしていれば「本体施設の利用者」にも「施設外就労の利用者」にも目標工賃達成指導員配置加算を算定することが可能です。
まとめ
就労継続支援B型の事業所で、目標工賃達成指導員配置加算を算定している場合、本体施設では「5:1」(目標工賃達成指導員、職業指導員、生活支援員)の職員配置が必要ですが、施設外就労においては「6:1」(支援員)の職員配置が必要ということになります。
また、施設外就労での人員配置を考える際には「本体施設」と「施設外就労」とを分けて考える必要があります。詳細については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和3年3月30日障障発0330第2号改正)を確認するようにしてください。
当事務所では、就労継続支援B型の運営コンサルティングサービスを提供しております。就労継続支援B型の運営でお困りの事業所様は当事務所の就労継続支援B型運営コンサルティングサービスをご利用ください。