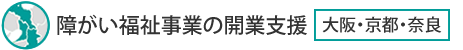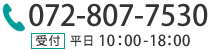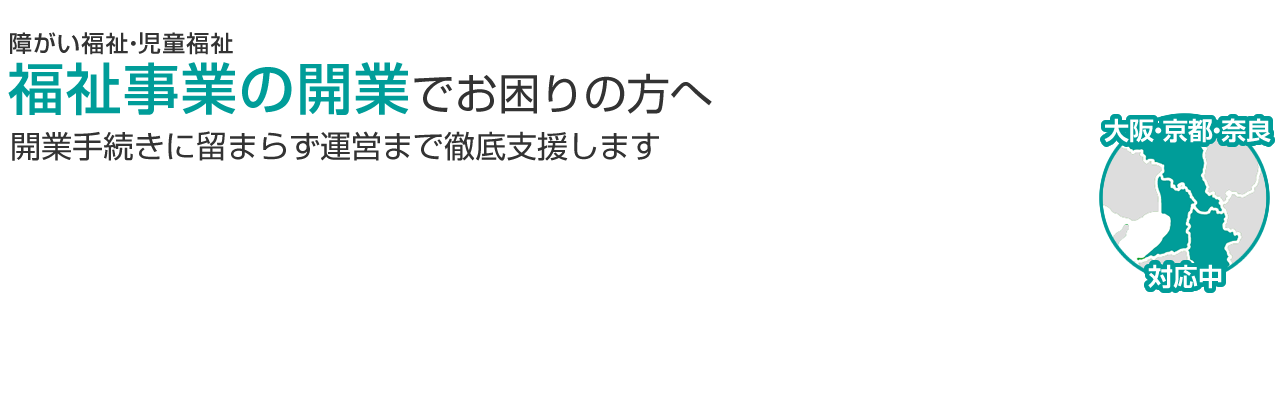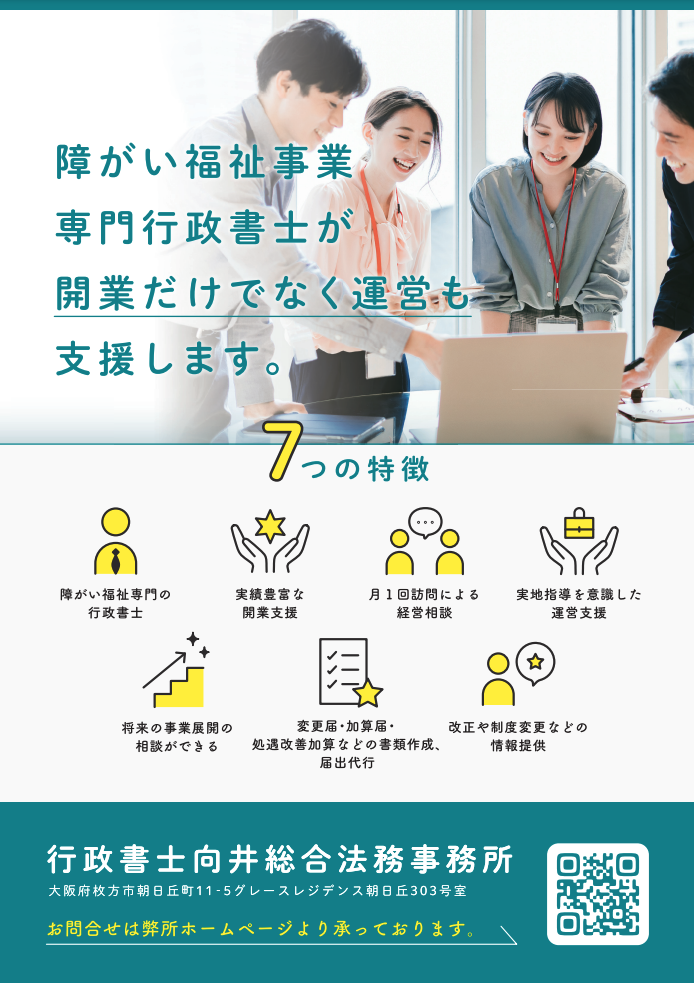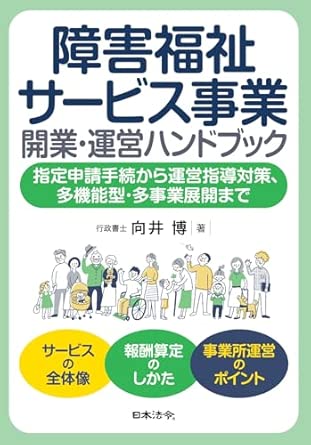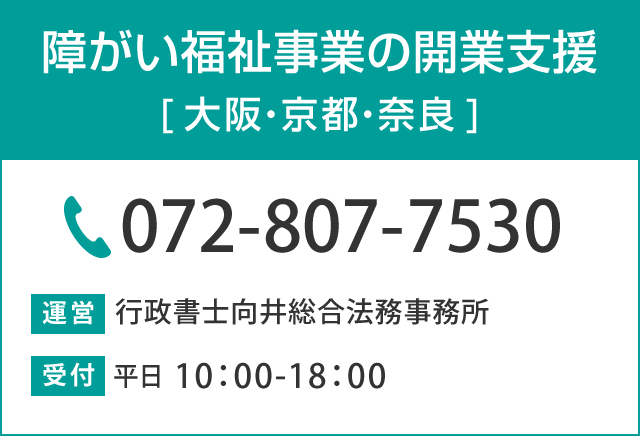障がい福祉サービス事業、児童福祉事業では、「身体拘束廃止未実施減算」「虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画未策定減算」「情報公表未報告減算」があります。うっかり忘れてしまいがちですので、毎年、年度初めの4月に年間スケジュールを作成し、漏れなく実施するようにしましょう。
身体拘束廃止未実施減算
障害福祉サービス事業や児童福祉事業では、身体拘束は原則として禁止されています。そのため、不適切な身体拘束がなされないように指針の整備や委員会の設置などが令和6年度報酬改定により義務化されました。身体拘束廃止未実施減算は、この取組みを怠ったときに適用される減算です。
対象サービス
- 障害福祉サービス事業では、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助。
- 児童福祉事業では、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所支援・共生型障害児通所支援・基準該当通所支援(みなし基準該当通所支援を除く)。
身体拘束廃止未実施減算の算定単位数
身体拘束廃止未実施減算は対象サービスによって減算率が異なります。
| 療養介護、施設入所支援、 障害者支援施設が行う昼間実施サービス、 共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所支援 |
所定単位数の 10%を減算 |
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、 自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援、 就移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、 児童発達支援、放課後等デイサービス、 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 (障害者支援施設が行う昼間実施サービスを除く) |
所定単位数の 1%を減算 |
※ここでの所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く)がなされる前の単位数をいいます。ただし、複数の減算事由に該当する場合には、各種減算したうえで得た単位数に対して減算率を適用します。
身体拘束廃止未実施減算の要件
身体拘束廃止未実施減算は、以下の取組みができていない場合に適用されます。
- やむを得なく身体拘束を行った場合に、記録が行われていない。
- 身体拘束適正化検討委員会を1年に1回以上開催していない。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
- 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない
やむを得なく身体拘束を行った場合に、記録が行われていない
身体拘束が行われたことに対してのペナルティではなく、やむを得なく身体拘束を行った場合に記録がなされていないことに対してのペナルティです。
緊急やむを得ない理由については、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件をすべて満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければなりません。
身体拘束適正化検討委員会を1年に1回以上開催していない
身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催していない場合、具体的には1年に1回以上開催していない場合に減算となります。
この身体拘束適正化検討委員会は、法人単位での開催でも問題ありません。また、虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可能です。ただ、開催の記録は同時開催であっても委員会ごとに別々に残しておくか、同じ記録でも内容を分けて記録するようにしましょう。
委員会はテレビ電話装置等(ex.Z00M)を活用して行うことでも構いません。ただし、障害者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うことが必要です。「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守することも必要です。
身体拘束等の適正化のための指針を整備していない
やむを得ず利用者の身体拘束をしなければならない場合の基準やルール、従業者が取るべき行動の指針を整備していない場合、減算となります。身体拘束等の適正化のための指針には以下のような内容を盛り込みましょう。
- 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
- 身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
- 身体拘束等の適正化の研修に関する基本方針
- 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
- 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない
身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない、具体的には、研修を1年に1回以上実施していない場合は、減算となります。
身体拘束等の適正化のための研修は、「1年度」に1回以上ではなく、「直近1年以内」に1回以上実施する必要があります(令和3年度報酬改定Q&A VOL1 問18)。
減算適用のタイミング
身体拘束廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から「改善が認められた月」までの期間、利用者全員について基本報酬の減算となります。
ここで「事実が生じた場合」とは、運営基準を満たしていない状況(上記の減算事由)が確認されたことを指します。例えば、運営指導で令和7年5月1日に運営基準を満たしていないと確認された場合は、令和7年6月サービス提供分から減算となります(令和3年度報酬改定Q&A VOL1 問19)。
減算事由が認められた場合には、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告する必要があります。
身体拘束廃止未実施減算は、共同生活援助(グループホーム)では、基本報酬の10%が減算となります。利用者全員についての減算ですのでインパクトは大きいです。身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と同時に開催するなど、効率よく運営していくようにしましょう。
虐待防止措置未実施減算
虐待防止措置未実施減算というのは、虐待の防止のための取組みが適切に行われていない場合は、所定単位数の1%が減算されるというものです。虐待防止措置未実施減算は令和6年度の報酬改定で新設されました。
対象サービス
すべてのサービス
虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1%減算
※ここでの所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く)がなされる前の単位数をいいます。ただし、複数の減算事由に該当する場合には、各種減算したうえで得た単位数に対して減算率を適用します。
虐待防止措置未実施減算の要件
虐待防止措置未実施減算は、以下の取組みができていない場合に適用されます。
- 虐待防止委員会を1年に1回以上開催していない。
- 虐待防止のための研修を定期的に開催していない
- 虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない。
虐待防止委員会を1年に1回以上開催していない。
虐待防止委員会を定期的に開催していない場合、具体的には、1年に1回以上開催していない場合に減算となります。
虐待防止委員会は、法人単位での開催でも問題ありません。また、身体拘束適正化委員会と一体的に設置・運営することも可能です。ただ、開催の記録は同時開催であっても委員会ごとに別々に記録し残しておくか、同じ記録でも内容を分けて記録するようにしましょう。
委員会はテレビ電話装置等(ex.Z00M)を活用して行うことでも構いません。ただし、障害者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うことが必要です。「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守することも必要です。
虐待防止のための研修を定期的に開催していない
虐待防止のための「研修」を定期的に開催していない、具体的には、1年に1回以上実施していない場合は、減算となります。
虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待防止のための研修の実施)を適切に実施するための担当者を配置していない。
委員会を適切に開催したり、研修・訓練を実施するために担当者を決めておく必要があります。
減算適用のタイミング
虐待防止措置未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から「改善が認められた月」までの期間、利用者全員について基本報酬の減算となります。
ここで「事実が生じた場合」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指します。例えば、運営指導で令和7年5月1日に運営基準を満たしていないと確認された場合は、令和7年6月サービス提供分から減算となります(令和3年度報酬改定Q&A VOL1 問19 身体拘束等未実施減算)。
※令和3年度報酬改正Q&A問19は、身体拘束等廃止未実施減算についての記載ですが、減算適用のタイミングが同じであること、研修の同時開催が認められていることから、当方は虐待防止措置未実施減算についてもあてはまるものと解釈しています。
減算事由が認められた場合には、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告する必要があります。
身体拘束廃止未実施減算や虐待防止措置未実施減算については、事業所が適切な措置を取らず、行政の改善の指導にも従わなかった場合には、行政は指定の取消しを検討することとなっています。
共同生活援助のような入所系の施設では身体拘束廃止未実施減算は10%減算とインパクトの大きいものですが、基本的には減算率は1%となっており、インパクトはあまり大きくありません。だからと言って適切な措置を実施していないと、行政の指導の対象となり、指定取消の対象となってしまいます。
身体拘束廃止や虐待防止というのは利用者の尊厳を守るためにも非常に重要なことでありますので、未実施の場合には厳しい措置が取られることになるのです。
業務継続計画未策定減算
業務継続計画とは、感染症や自然災害が発生した場合に、利用者へのサービス提供を継続して行い、非常時でも早期に体制を整え業務を維持・継続していくための計画のことをいいます。一般的にBCP(Business Continuity Planning)と言われています。
障害福祉サービス事業所・児童福祉事業所には、感染症や自然災害の発生に備えてこの業務継続計画(BCP)を策定する義務があります。業務継続計画が策定できていない場合には、業務継続計画未策定減算が適用され減算となります。令和6年度の報酬改定で新設された減算項目です。
対象サービス
すべてのサービス
業務継続計画未策定減算の算定単位数
業務継続計画未策定減算は対象サービスによって減算率が異なります。
※就労選択支援については経過措置があり、令和9年3月31日までは、業務継続計画未策定減算は適用されません。
※ここでの所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く)がなされる前の単位数をいいます。ただし、複数の減算事由に該当する場合には、各種減算したうえで得た単位数に対して減算率を適用します。
業務継続計画に記載する項目
業務継続計画は、「感染症」と「自然災害」の両方の計画を策定しなければなりません。
「感染症」の業務継続計画に記載する項目
- 平常時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、装備品の確保等)
- 初動対応
- 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
「感染症」に係る業務継続計画の研修・訓練
- 障害者支援施設・・・定期的に、年2回以上実施 + 新規採用時
- 障害者支援施設以外・・・定期的に、年1回以上実施 + 新規採用時
※感染症の予防及びまん延防止の研修・訓練と兼ねても可。
「自然災害」の業務継続計画に記載する項目
- 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策。必要品の備蓄等)
- 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
- 他施設及び地域との連携
「自然災害」に係る業務継続計画の研修・訓練
- 障害者支援施設・・・定期的に、年2回以上実施 + 新規採用時
- 障害者支援施設以外・・・定期的に、年1回以上実施 + 新規採用時
研修・訓練の記録は必ず作成し保管するようにしましょう。
減算のタイミング
業務継続計画の策定及び業務継続計画に従い必要な措置を講じていない事実が生じた場合に、「その翌日(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日がある場合は当該月)」から「基準に満たさない状況が解消されるに至った月」まで、当該事業所の利用者全員について、減算されます。
各委員会まとめ
| 項目 | 委員会開催 | 研修・訓練 |
|---|---|---|
| 虐待防止委員会【減算あり】 | 年1回以上 | 研修:年1回以上+新規採用時 |
| 身体拘束適正化検討委員会【減算あり】 | 年1回以上 | 研修:年1回以上+新規採用時 |
| 感染対策委員会 | Aグループ:6ヶ月に1度 Bグループ:3ヶ月に1度 |
研修:年2回以上+新規採用時 訓練:年2回以上 |
| 業務継続計画(BCP)策定【減算あり】 ・感染症に係る業務継続計画 ・災害に係る業務継続計画 |
― (定期的な見直し必要) |
研修:年1回以上+新規採用時 訓練:年1回以上 (支援施設は年2回以上) |
<感染対策委員会>
Aグループ/訪問系サービス、相談系サービス、就労定着支援、自立生活援助
- 対象範囲は「感染症の予防および蔓延防止」のみ
- 開催頻度は6ヶ月に1度以上
- 専任の感染症対策担当者を決めておく
- 構成委員に指定はない
- 他のサービス事業者との連携の指定はない
Bグループ/生活介護、就労移行、就労AB、共同生活援助(GH)、児発、放デイ、短期入所
- 対象範囲は「感染症の予防および蔓延防止」に加えて「食中毒の予防」
- 開催頻度は3ヶ月に1度以上
- 専任の感染症対策担当者を決めておく
- 構成員は複数の職種による混成が必要(食事提供体制加算を算定している場合は調理員も参加)
- 事業所以外の感染管理等の専門家との連携が望まれる。
<業務継続計画BCP>
「感染症の業務継続計画」に係る研修・訓練については、「感染症の予防及びまん延防止」のための研修・訓練と一体的に実施することも差し支えない。
情報公表未報告減算
令和6年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、利用者への情報公表や災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、令和6年4月1日より、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所は減算となります。
対象サービス
全てのサービス
情報公表未報告減算の要件
障害者総合支援法76条の3及び児童福祉法33条の18の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない
情報公表未報告減算の算定単位数
情報公表未報告減算は、対象サービスによって減算率が異なります。
| 療養介護、施設入所支援、 障害者支援施設が行う昼間実施サービス、 共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設 |
所定単位数の 10%を減算 |
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、 自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、 就労選択支援、就労定着支援、就移行支援、 就労継続支援A型、就労継続支援B型、地域移行支援、 地域定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 (障害者支援施設が行う昼間実施サービスを除く) |
所定単位数の 5%を減算 |
※ここでの所定単位数は、各種加算(障害福祉サービス費等の報酬算定構造表において当該減算より左に規定されている加算を除く)がなされる前の単位数をいいます。ただし、複数の減算事由に該当する場合には、各種減算したうえで得た単位数に対して減算率を適用します。
減算のタイミング
情報公表未報告減算については、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合に、「その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)」から「報告を行っていない状況が解消されるに至った月」まで、利用者全員について減算されます。
情報公表の方法
独立行政法人福祉医療機構からログインIDやパスワード等が記されたメールが各事業所宛てに送信されますので、「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」にログインし、必要事項を入力のうえ、承認申請を行います。承認申請は新規に指定を受けた時のほか、毎年行う必要があります。報告期間は次の通りです。
- 新規に指定を受けた事業者にあっては、指定を受けた日から1ヶ月以内
- その他の事業者にあっては、毎年5月1日から7月31日まで
当事務所では、顧問先企業様限定ですが、各種委員会での指針や業務継続計画(BCP)作成のコンサルティングサービスを行っております。
※ひな型の販売は行っておりません。
※無料相談は行っておりません。