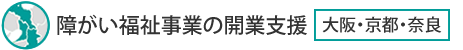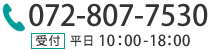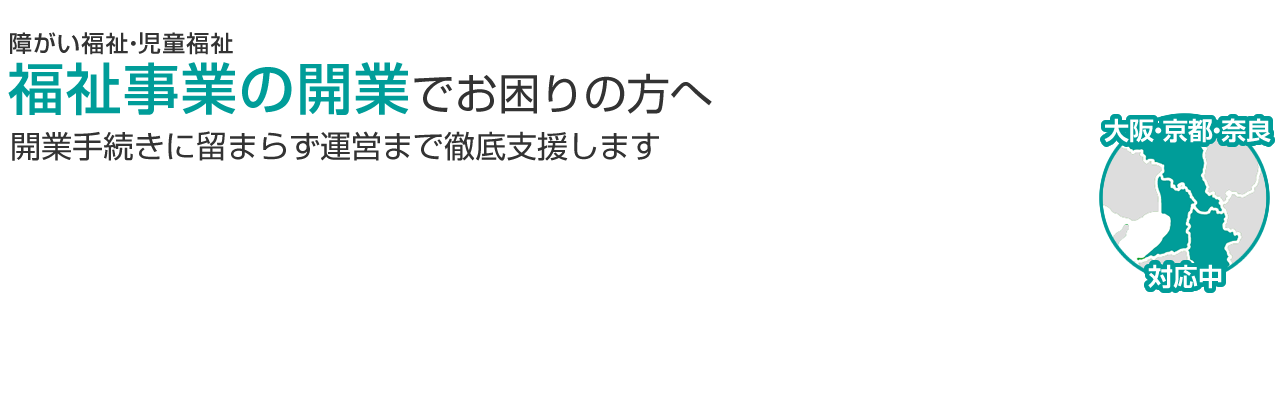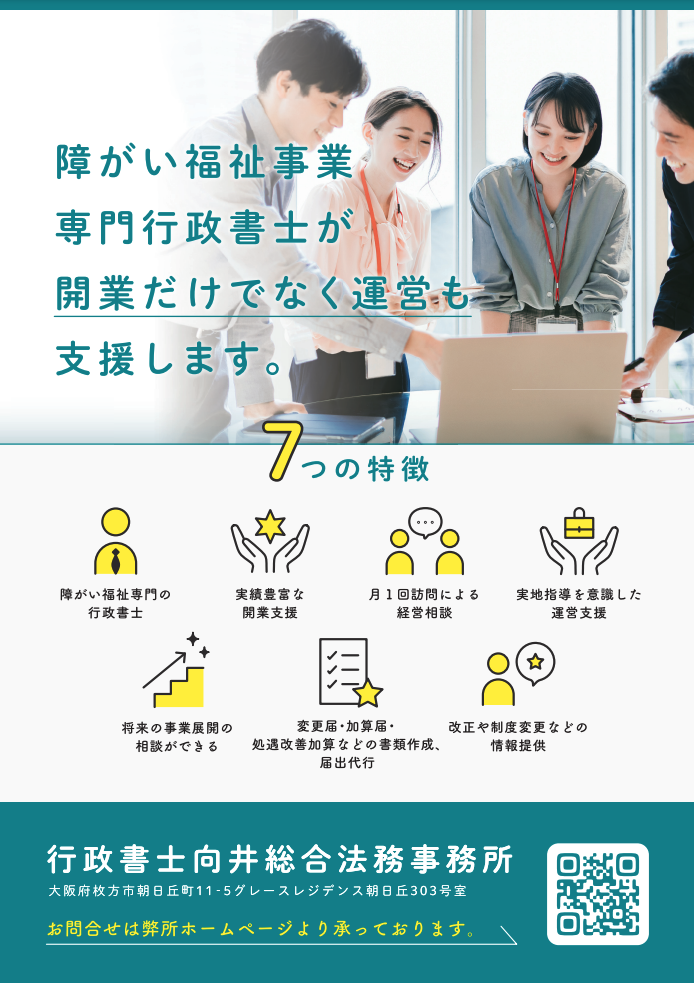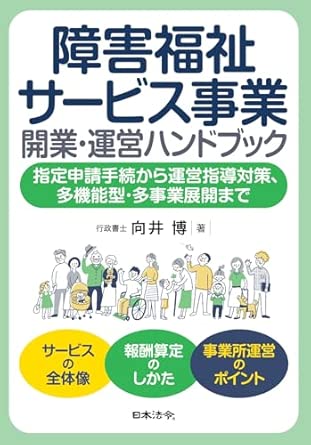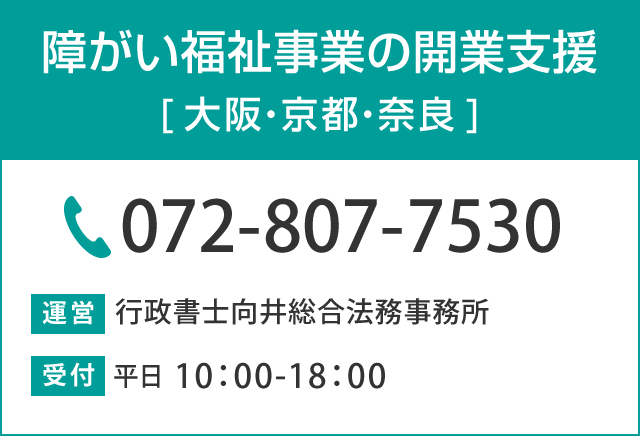就労継続支援B型事業は、一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的とした事業をいいます。就労継続支援事業にはA型とB型の2種類があり、A型は障がい者と雇用契約を締結し、原則として最低賃金を保証する「雇用型」で、B型は雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける「非雇用型」となっています。
具体的には、次のような方が対象者となります。
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
③ 上記①、②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者
目次
就労継続支援B型事業の開業手順
就労継続支援B型を開業するためには、就労継続支援B型の「指定」を受ける必要があります。「指定」というのは、いわば障がい福祉サービス事業を開業したり運営したりしていくためのライセンスのようなものです。
1.就労継続支援B型を開業し運営する法人を設立する
就労継続支援B型で指定を取るためには、運営主体が法人格を有していなければなりません。個人事業主では就労継続支援B型の指定を受けることができません。
ただ、就労継続支援B型を運営する法人といっても株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人など、いくつかの種類があります。最近は、設立費用が比較的安くで済む合同会社が増えているようです。合同会社は「Limited Liability Company」の略で「LLC」とも表記され、会社法で認められた法人形態です。そこで、合同会社のメリット・デメリットをみてましょう。
【合同会社のメリット】
① 設立費用、ランニングコストが他法人に比べて安い
合同会社の場合、定款の認証が不要なため、株式会社では必要とされた定款の認証手数料50,000円が不要です。また、電子定款にすれば定款用収入印紙代40,000円が必要なくなります。
② 経営上の事務作業の負担が少ない
株式会社では役員任期を決める必要がありますが、合同会社では任期を決める必要がありません。そのため、合同会社の場合は、任期更新時の重任登記の手続きは不要とすることができます。また、株式会社の場合は決算を公告する義務がありますが、合同会社の場合には広告の義務がないため、公告のための事務作業や費用の負担が少なくてすみます。
③ 経営の自由度が高い。
株式会社の場合は、出資比率に応じて利益を分配する必要がありますが、合同会社の場合は、出資比率に関係なく社員間で自由に利益の配分を行えますので、貢献度に応じた利益配分が可能です。また、定款による組織の設計の自由度も高く、出資者と経営者が一致しているため、株主総会などを経ずに迅速に意思決定ができます。
【合同会社のデメリット】
① 他法人に比べて信用度はやや劣る
合同会社の場合は、株式会社と比較してその信用度はやや劣ってしまいます。
② 株式会社と合同会社では役員の肩書が違う
デメリットというよりも好みの問題ですが、代表者の肩書が、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。代表取締役を名乗りたいのであれば合同会社ではなく株式会社ということになります。
③ 合同会社では株式を使った資金調達ができない。
株式会社では、株式を対価に資金調達することができますが、合同会社では、株式を使った資金調達ができません。大きく会社を成長させるつもりなら株式会社の方が適している場合があります。
以上のように、合同会社にはメリットもデメリットもありますので、法人を設立する際は就労継続支援B型の事業をどのように展開していくのかも考えながら法人形態を選ぶようにしましょう。
ただし、当事務所では、できるだけ株式会社での開業をお勧めしています。最近では、NPO法人はもとより、一般社団法人や合同会社では開業後に銀行から融資を受けようとした場合に、銀行によっては融資を受けにくくなっているようです。合同会社を設立して開業した場合、後々の事業展開の際に銀行融資を受けようとして、信用力を上げたいということから合同会社から株式会社に組織変更を望まれる法人様もあります。組織変更となると時間も費用もかかりますので、それであれば最初から株式会社での開業をされた方が無難でしょう。そのため、当事務所ではとくに法人形態にこだわりがないのであれば、合同会社よりも設立費用はかかりますが、「株式会社」をお勧めしております。
2.都道府県(市町村)から就労継続支援B型の「指定」を受ける
都道府県(市町村)ごとに就労継続支援B型の指定申請手続きのスケジュールが決められています。その決められた就労継続支援B型の指定申請スケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をすすめていくことになります。就労継続支援B型の指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が決まることになります。
例えば、
- 大阪市の場合 事前協議 → 指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定
- 京都市の場合 事前相談 → 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定
- 奈良市の場合 事前相談 → 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定
この段階でのご相談でよくあるのが、あまりにも短い期間での指定日を希望されるご相談です。
就労継続支援B型として使用する物件の選定具合や人員の確保具合にもよりますが、行政側の就労継続支援B型の指定申請のスケジュールは決まっていますし、一定の審査期間はどうしてもかかってしまいます。
大阪市の場合であれば、指定日前月10日から翌月1日まで、京都府であれば申請が受理されてから概ね1ヶ月間の期間は見込んでおかなければなりません。この期間に相談支援事業所へ開業の挨拶回りやスタッフ研修などの開業準備をしていきましょう。これらの細々とした就労継続支援B型の開業準備をしっかりしていると意外と時間が喰われますのであっという間に指定日を迎えることになります。
就労継続支援B型の事前協議(事前相談)の次は、指定申請を行います。就労継続支援B型の指定申請では、就労継続支援B型として使用する物件が適法な状態であることや人員基準を満たしていることなどを証明するために各種資料の収集や申請書類を作成していくことになります。
就労継続支援B型の指定申請書類一覧(例:大阪市)
| 必要(添付)書類 |
|---|
| 指定申請に係る提出書類一覧表 |
| 指定申請書 |
| 指定に係る記載事項(付表) |
| 履歴事項証明書 |
| 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
| 組織体制図 |
| 管理者の経歴書 |
| サービス管理責任者の経歴書 |
| サービス管理責任者の資格要件を証する書類 |
| サービス管理責任者の実務経験証明書 |
| 相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了証の写し |
| サービス管理責任者基礎研修・実践研修修了証の写し |
| 従業者の資格を証明するもの(資格証の写しなど) |
| 事業所(建物)の平面図 |
| 事業所(建物)内外の写真 |
| 事業所建物にかかる賃貸借契約書の写し or 登記事項証明書の原本 |
| 建築基準法に基づく確認申請書の写し and 検査済証の写し |
| 建築士による採光換気証明書 or 法人による採光換気計算書 |
| 防火対象物使用開始届の写し |
| 居室面積等一覧表 |
| 設備・備品等一覧表 |
| 運営規程 |
| 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
| 協力医療機関との契約内容 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 |
| 案内図 |
| 主たる対象者を特定する理由(特定する場合のみ) |
| 事業計画書 |
| 収支予算書 |
| 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類 |
| 障害福祉サービス事業等開始届 |
| 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
| 訓練等給付費の算定に係る体制状況一覧表 |
| 加算を算定する場合に必要な書類(介給別紙等) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算届出書類(計画書、届出書) |
| 業務管理体制の整備に関する事項の届出書 |
| 障害福祉サービス等情報公表用法人メールアドレスの登録について |
就労継続支援B型の指定申請の際には、様々な多くの書類を作成していくことになります。大きなポイントとなる部分を挙げるとすれば、Ⅰ:人員基準、Ⅱ:物件の適法性・設備基準、Ⅲ:生産活動の内容 Ⅳ:協力医療機関の同意 がポイントとなります。
Ⅱ 就労継続支援B型として使用する物件の間取りが適切で、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)、消防法に適合しているか。就労継続支援B型の設備基準を満たしているか
Ⅲ 生産活動はどのようなものを行い、工賃はどれくらい払えるのか
Ⅳ 協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか
Ⅰ.就労継続支援B型事業を開業するためには、就労継続支援B型事業の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。
就労継続支援B型事業の指定申請が収受されるためには、サービス管理責任者を中心とした就労継続支援B型の
人員配置が非常に重要となります。
また、人員配置は指定を取得した後(開業後)の就労継続支援B型の運営面でも非常に重要となる基準になります。サービス管理責任者の要件と一緒に正しく理解しておきましょう。
指定就労継続支援B型事業の人員基準
| 職 種 | 就労継続支援B型の人員配置基準 | 常勤要件 | 備考 |
| 管理者 | 1名以上 | 兼務可 | |
| サービス 管理責任者 |
・利用者60人以下…1人以上 ・利用者60人以上…1人に、利用者が60人を超えて40 or その端数を増すごとに+1人以上 |
常勤 | ・資格要件 ・実務経験 ・研修要件 |
| 職業支援員 | 常勤換算で、利用者数を 10 or 7.5 or 6 で除した数以上 | どちらか1人は 常勤 |
資格不要 |
| 生活支援員 |
Ⅱ.就労継続支援B型事業を開業するためには、物件の間取りが適切であり、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)、消防法に適合していなければなりません。
就労継続支援B型事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。用途変更の確認申請には、原則として「確認済証」と「検査済証」が必要になりますが、その手続きは負担も費用も大きなものになるが通常ですので、就労継続支援B型の物件を選ぶ際には、できるだけ使用部分が200㎡以下の物件を選ぶようにしましょう。
そして、京都府や京都市ではバリアフリー関係の手続きや工事が絡むことになりますので、指定申請が完了するまでに比較的時間がかかります。バリアフリー条例やまちづくり条例がかかる物件では、建築担当部署との協議が必要になります。既存の物件であっても協議を繰り返し、必要な工事を確定していき、工事を経て、建築担当部署の職員による完了検査を経る必要があります。物件や建築士などの経験にもよりますが、このバリアフリー関係の手続きや工事だけでも概ね3ヶ月~6ヶ月はかかるのが通常です。
物件探しをはじめられるとわかると思いますが、今はどこの事業所も新しい事業所としての物件を探しています。そのため、なかなか適切な物件が見つからない状況です。どうしても適度な大きな物件が見つからないようであれば、「主たる事業所」と「従たる事業所」を分けて指定を取る方法もあります。これであれば、一体で指定を取るよりも狭い物件で指定を取ることが可能となります。ただ、定員20名であれば、「主たる事業所」で10人、「従たる事業所」で10人とし、どちらにも常勤職員の配置が必要になるなど、一体で指定を取る場合とは要件が異なりますので注意しましょう。
また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけない場合がありますので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。さらに、以下の設備要件を満たしていることが必要です。
指定就労継続支援B型事業の設備基準
| 設 備 | 要 件 |
|---|---|
| 訓練作業室 | サービス提供に支障のない広さを備えること。大阪市の場合は、利用者1人当たり約3.0㎡必要。 就労継続支援B型事業は、最低定員20名。訓練指導室の最低面積は60㎡(20名×3㎡)が必要。 |
| 相談室 | プライバシーに配慮していること。 |
| 多目的室 | 相談室と兼務可能。 |
| 事務室 | 鍵付き書庫を設置すること。 |
| 洗面所・トイレ | 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。 |
Ⅲ.就労継続支援B型の生産活動としてどのような内容のものを行うのか
就労継続支援B型の場合、生産活動で支払われる利用者の平均工賃が給付金の単価に影響します。利用者への平均工賃が上がれば単価も上がり、平均工賃が下がれば単価も下がります。そのため、生産活動でどのような活動を行い、その活動によってどれだけの売上をあげ、利用者へどれだけの工賃を支払うのかを考えておく必要があります。
最近増えてきているのが、カフェや飲食店での収益を生産活動収益とする就労継続支援B型です。定員20人の就労継続支援B型の場合、多くの自治体で60㎡の訓練作業室を確保する必要があります。カフェや飲食店の場合、調理スペースだけでなく接客スペースや飲食スペースも訓練・作業室に含めることができますので、60㎡のなかにスタッフも利用者さんもカフェのお客様も集まることになります。そうすると、60㎡で指定基準はクリアできるのですが、現実的には非常に狭い状況になってしまいます。そのため、物件を探す場合には、訓練作業室として60㎡以上のものを探すのはもちろんなんですが、生産活動でカフェや飲食店をするのであれば訓練作業室はもう少し余裕のある大きさの物件を探す方が良いかと思います(ただし、使用する部分が200㎡以上となると建築関係の用途変更の手続きが必要になりますので避けるようにしましょう)。つまり、物件を探す場合にはできるだけどのような生産活動をするのかをイメージしながら探すようにしましょう。
自治体によっては就労継続支援B型の場合でも、生産活動の「収支計画」や「作業量積算根拠」がわかる資料の提出が求められることがあります。就労継続支援B型の生産活動の収支計画では一月あたりの平均工賃が3,000円以上になるように計画をたてます(基準省令第201条)
Ⅳ.協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか
就労継続支援B型事業所を運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良を起こしたり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。
はじめて指定申請をする場合、この協力医療機関の同意(ハンコ)を取るのに非常に苦労する方もいらっしゃいます。就労継続支援B型の開業手順のはやい段階で協力してくれそうな医療機関に打診しておきましょう。
3.就労継続支援B型の「指定」を取得
就労継続支援B型の指定申請書類が収受されて審査を経たのちに、ようやく就労継続支援B型の「指定」を取得することができます。
就労継続支援B型の指定を取得することももちろん大切ですが、指定を取得した後の「運営面」こそが重要になります。指定を取得することによってようやく事業運営のスタートラインに立てたといっても過言ではありません。
とくに、就労継続支援B型事業のような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。障がい福祉サービス事業の事業所収益は税金が投入されているからです。当事務所では、法令に適合した運営を行いつつも事業所としての収益を上げれるような運営コンサルティングサービスを行っております。
また、就労継続支援B型事業所を開業し運営を行い、事業所としての運営に慣れてくれば次の事業展開として、就労継続支援B型の事業所に通所されている利用者さんの居住サービスである共同生活援助(グループホーム)を検討される事業所さんも多いです。就労継続支援B型の利用者さんの親御さんから「良いグループホームが見つからない・・・」という声も多いのが現実ですので、地域の福祉のためにも検討されてみてはどうでしょうか?
就労継続支援B型事業の指定申請手続き(開業手続き)に詳しい行政書士が開業支援
就労継続支援B型事業所をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって申請スケジュールが決められています。その決められたスケジュールに合わせて、調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければ事業開始時点(指定日)がどんどん後ろにズレてしまうことになります。これではいつまで経っても開業できず売上をあげられないのに、物件家賃や従業員給料などの経費が出ていくだけになってしまい、資金繰りに窮してしまいます。実際に、就労継続支援B型の指定はとれたのは良いのですが、2~3ヶ月で廃業してしまう事業所さんもあるのです。
そうならないためには、就労継続支援B型事業の収支予算シミュレーションを考えながら開業時点(指定日)を目標設定することにより、就労継続支援B型の指定申請のために必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなくてはなりません。就労継続支援B型として使用する物件の賃貸借契約の締結や従業員との雇用契約のタイミングも就労継続支援B型の指定日を明確にすることによって、物件の賃貸契約のタイミング、雇用契約のタイミングが見えてくるのです。
また、建築基準法の用途変更や消防法の消防設備の設置工事などが必要になると建築士や消防設備業者との連絡調整も必要になりますし、行政の各担当部署ともすり合わせが必要となってきます。事業開始時点という就労継続支援B型の「指定日」を目指して一つ一つ手続きをクリアしてことになります。
これらの就労継続支援B型の指定申請の手続きをスケジュールどおりに行うには就労継続支援B型の指定申請に詳しい実績の豊富な行政書士でなければ難しいでしょう。就労継続支援B型事業の指定申請手続きの経験のない行政書士やコンサルタントが手続きを受任して「就労継続支援B型の開業の準備途中で挫折してしまった・・・」「いつまでたっても就労継続支援B型を開業できない・・・」という話はこの業界ではよく聞く話です。
当事務所では、就労継続支援B型事業の指定申請の実績も豊富でございます。指定後の就労継続支援B型の運営面も見据えた指定申請を行っていきましょう。
当事務所に就労継続支援B型の開業支援をご依頼いただく3つのメリット
就労継続支援B型の指定申請手続きだけではありません!!開業後を見据えた指定申請が大切です。
当事務所では、単に「指定申請手続き」といった就労継続支援B型の開業時の手続きのみに対応するだけではありません。指定申請後の就労継続支援B型の運営面を見据えたコンサルティングも行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算や食事提供体制加算をとるにはどのような要件をそろえればその「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの「売上」が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら就労継続支援B型の指定申請の手続きをすすめていきます。
就労継続支援B型の加算でできれば算定したい加算しては目標工賃達成指導員配置加算です。目標工賃達成指導員配置加算は報酬単価が高いので、算定することができれば売り上げも上がることになります。ただ、就労継続支援B型の開業時からこの目標工賃達成指導員配置加算を算定することも可能なのですが、算定要件として基本の人員配置に加えて常勤換算上1人分の従業者の配置が必要になります。そのため、人件費のことを考えれば一般的に人員基準が緩和される開業後6ヶ月経過した時点(7ヶ月目)から目標工賃達成指導員配置加算を算定するのもかしこい加算の取り方と言えるでしょう。
さらには、指定申請時に思うように職員が集まらないようであれば、報酬単位の高い「6:1」の職員配置をあきらめて「7.5:1」や「10:1」の職員配置で指定申請を行うことも検討するべきでしょう。
そして、就労継続支援B型の事業所を運営するということは従業員の給料はもちろん家賃などの経費を支払っていかなければなりません。就労継続支援B型の収支を意識した事業所運営を行いましょう。
就労継続支援B型の指定後(開業後)の運営コンサルティングにも対応!!
障がい福祉サービス事業は、事業所の収益に税金が投入されるわけですから、厳しいコンプライアンス(法令遵守)が求められる業界です。就労継続支援B型事業のような日中活動系・就労系といわれるような事業でも定期的に行政による運営指導は入ります。いいかげんな就労継続支援B型の運営をしていては、行政から報酬の返金を求められたり、最悪の場合は指定取消となってしますケースもあります。当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス(法令順守)経営が両立するような就労継続支援B型の運営コンサルティングサービスを行っております。
就労継続支援B型の開業時の創業融資にも対応しております!!
就労継続支援B型事業を含む障がい福祉サービス事業では、サービスを提供した月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)に報酬請求を行います。ただ、その入金はさらに翌月の中頃になります。つまり、入金サイト(入金期間)が他の業種に比べて比較的長いのが特徴です。そのため、就労継続支援B型の開業時には開業費用の他に最低でも6ヶ月程度の運転資金を準備しておかなければ就労継続支援B型の開業後すぐに資金ショートを起こしてしまう可能性があります。
当事務所では、日本政策金融公庫などの金融機関への創業融資の申込みのお手伝いもさせていただいております。就労継続支援B型の開業後では良くも悪くも実績ができてしまいますので融資が降りにくくなるといわれています。就労継続支援B型の開業前に余裕のある運営資金の準備をしておきましょう。
また、できれば日本政策金融公庫だけではなく、信用保証協会と金融機関が実施している制度融資も利用することを検討してみましょう。あまり融資金額が大きくなりすぎると利息も大きくなり返済が大きな負担となってしまいますが、きちんと約定通りに返済できるのであれば金融機関からの信用も大きくなり以後の融資が通りやすくなります。
就労継続支援B型事業の開業ご依頼の際の流れ
① 就労継続支援B型として使用する「物件」の目途をつけましょう。
就労継続支援B型として使用する物件の目途がついた段階では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は担当役所との就労継続支援B型の事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。
就労継続支援B型事業は、就労の機会を提供する場ですので、生産活動の内容にもよりますが、駅近のテナントビルというよりも少し郊外の比較的家賃の安い賃貸物件であるのが一般的です。就労継続支援B型の利用者さんに利用してもらわないと収益をあげることができませんので、就労継続支援B型としての「売り」になる生産活動を考えて利用者さんに選んでもらえるような就労継続支援B型事業所を目指しましょう。
また、自治体によってはバリアフリー関係の法令に適合していることも求められます。担当部署と協議を経て、計画に沿って内装工事を行い、現場での立会によって法令に適合していることを確認されます。
② 就労継続支援B型のサービス管理責任者を確保しましょう。
サービス管理責任者は就労継続支援B型事業を運営していくうえで非常に重要なポジションにあります。サービス管理責任者は、資格要件・実務経験・研修要件によって成れるか成れないかが決まりますが、労働市場に要件を満たすサービス管理責任者が不足しているのが現状です。これから事業を一緒に盛り上げていく仲間として働いてくれる人をはやい段階で確保しておきましょう。
また、サービス管理責任者については、任用要件が複雑化しています。以前は実務経験に加えて「相談支援従事者初任者研修(2日過程)」と「サービス管理責任者研修」の二つの研修を受講していればよかったのですが、現在では「サービス管理責任者研修」が「サービス管理責任者基礎研修」と「サービス管理者実践研修」になり、その間にOJT(原則として2年間)が必要になりました。
③ 当事務所へ就労継続支援B型の開業支援を依頼しましょう。
上記1.2の目途がついた段階で就労継続支援B型の開業支援ご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。
就労継続支援B型の開業支援の当事務所の報酬
| 料金 | 380,000円(税別) |
|---|
※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。
※建築士の用途変更や消防設備業者の工事などの費用は担当業者との別途契約となります。
※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途料金となります。
※創業融資などの融資手続きは別途契約となります。
就労継続支援B型の開業支援をご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料
- 就労継続支援B型として使用する物件の情報
物件の位置(住所地)、間取り(窓の位置・面積がわかれば尚良)、面積がわかるもの - 就労継続支援B型のサービス管理責任者の情報
履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー - 就労継続支援B型を運営する法人の定款・登記簿
定款の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。
適切でなければ変更手続きをする必要があります。